

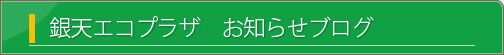
うべ環境コミュニティー主催 2025年度第1回「こころを語る会」が開催されました
2025年07月31日
うべ環境コミュニティーでは、「こころ」に関連するテーマについて、多様な年代、価値観、背景を持つ参加者が本音で語り合う会を開催しました。今回はこころの回復力{レジリエンス}を主要テーマとして、2024年度に開催した第1回~第3回「こころを語る会」の実績を踏まえて、具体的なレジリエンス向上の取り組みを行うこととしました。
[目的と要約]
一般のセミナー・講演会は座学が主体であるのに対して、「こころを語る会」では、参加者同士の対話、心理学ミニワークショップの実施により、参加者が積極的に「心のしなやかさの強化」(レジリエンス、即ちネガティブな心状態からの回復力強化)を如何にして獲得するのかについて、話し合ってきました。2025年度の第1回(7月19日)では、各参加者のレジリエンスの自己理解を図りました。レジリエンスの要因に関する問いに考えることを通して、参加者が自らの強みを振り返りました。また、レジリエンスを高める方法について心理学の観点で学んでいただきました。また、絵本と対話を通してレジリエンスを考える、こころの対話も進めました。
最終回(第3回「こころを語る会」(12月20日)に向けて、各自で生活に取り入れることになりました。3回目では再度、各自が問いを通してレジリエンスを振り返り、その変化を話し合う予定です。
開催日時
令和7年7月19日(土) 13:30~16:00 「こころの語り場」を実施
場所
宇部フロンティア大学 臨床心理学実習室
参加者
今回は酷暑の中での開催となり、体調不良で直前に欠席者が複数名でましたが、最終的に高校生・大学生;4名、社会人4名、シニア層6名、大学関係者2名の合計16名が参加し、色々な年齢層の方の対話を進めることが出来ました。
参加費 無料
プログラム
13:30~13:40 オープニング 薄井
13:40~14:55 レジリエンスの自己理解とワーク
14:55~15:05 休憩と準備
15:05~15:55 絵本のワーク 三島
15:55~16:00 エンディング 薄井
「各セッションの記録」
1.レジリエンスの自己理解
レジリエンスの尺度(こころの物差しになる質問群)が示され、質問への回答を通して、自らのレジリエンスを振り返りました。希望者は、回答をオンラインまたは郵送でフロンティア大学三島先生に送り、その回答のレーダーチャートと、振り返りを促すための問いかけを送っていただくことになりました。現在、6名の方が希望されています。
ただし、今回は一般のワークショップであり、臨床の場ではないので、三島先生が個人の心の状態を評価したり、個人的な相談に乗ることはできませんのでご留意ください。また、レジリエンスの尺度だけでは、ほんの一面しか捉えることはできませんので、コメントも参加者が考えるヒントになるような問いかけになっています。
【使用した尺度】
※“I can”“I am”“I have”“I like”という4つの観点で捉えた尺度
森 敏昭・清水 益治・石田 潤・富永 美穂子・Hiew, C. C.(2002)大学生の自己教育力とレジリエンスの関係.学校教育実践学研究,8,179-187.
※「楽観性」「統御力」「社交性」「行動力」という資質的レジリエンス要因,「問題解決志向」「自己理解」「他者心理の理解」という獲得的レジリエンス要因を捉えた尺度
平野真理(2010)レジリエンスの資質的要因・獲得的要因の分類の試み―二次元レジリエンス
要因尺度(BRS)の作成, パーソナリティ研究, 第 19 巻 第 2 号 94–106
2.レジリエンスの自己理解とワーク
自分のこころの中にあるレジリエンスに気付き、それを伸ばすためのワークを実施しました。
①自分と大切な人をそれぞれ円で表現するワークを通じて、人からの支えを大切なものと自覚する。
②多様な価値観のリストの中で、大切にしているものは何か、絶対に譲れない大切な元は何かを、どんどんチェックしていくワークを実施しました。これらの大切なことをどのように守ってきたのか、また絶対に譲れない大切なものをどう守っていきたいのか、自分で再発見していきましょう。
③レジリエンスが働いた体験を、横軸は時間経過、縦軸はこころの元気さや落ち込みの程度で図に描くワーク。こころの回復に役立った要素をできるだけ沢山書き出すワーク。
④好きなものを大切にする⇒宝箱の絵を見て、中に入っている私の宝物は何かをできるだけ沢山リストアップする。また、何でも体験できるチケットをもらったとき、どんなことがしたいかを答えるワーク。
日常生活でレジリエンスを高めるために、色々と取り組むべき行動のヒントが示されました。
・リラクゼーション呼吸法
・価値観と行動を一致させる「マインドセット」の5分間ホームワーク
・幸福と親切の因果関係(一週間のうち曜日と時間を決めて親切な行動を取ろう)
・人に親切にすることで、自分の強みを引き出す
・セルフ・コンパッション-自分の苦しみや悲しみ等に気付き、慈しみ和らげる-(今日頑張った自分を思いやる言葉を、自分にかけてあげよう)
・前の自分と今の自分、将来の自分を比較して、今頑張っていることを一つ挙げよう。そして1年前と比べてどう変化してきたか、1年後に頑張り続けることでどのように変化しそうかを、書き出してみよう。
・感謝することが、感謝している人自身の幸福感を高めます。週1回、ありがたかったことを記録する。「今日あったこと 感謝する相手と感謝の言葉 今の気分がどうなのか」について感謝日記をつけよう。
3.絵本のワーク
参加者はテーブルに置かれた気になる絵本を各自、1冊選んでざっと読んでみる。各テーブルの約5名でグループを作り、自分が選んだ絵本の概要を説明する。中で共通して読み合わせをする1冊の絵本を選ぶ。次に交代で2~3ページを分担して、音読する。この絵本でレジリエンスがどのように描かれているのか、あるいは感想や思いを伝え合う。時間が十分あったので、各自が選んだ絵本についての思いや感想を披露して、それに対してグループ内でレジリエンスと絡めて対話・意見交換を行った。
全体会での発表の時間はとれなかったが。グループ内での意見の共有と、相手の言わんとすることに対する共感と理解は十分得られたと思われる。
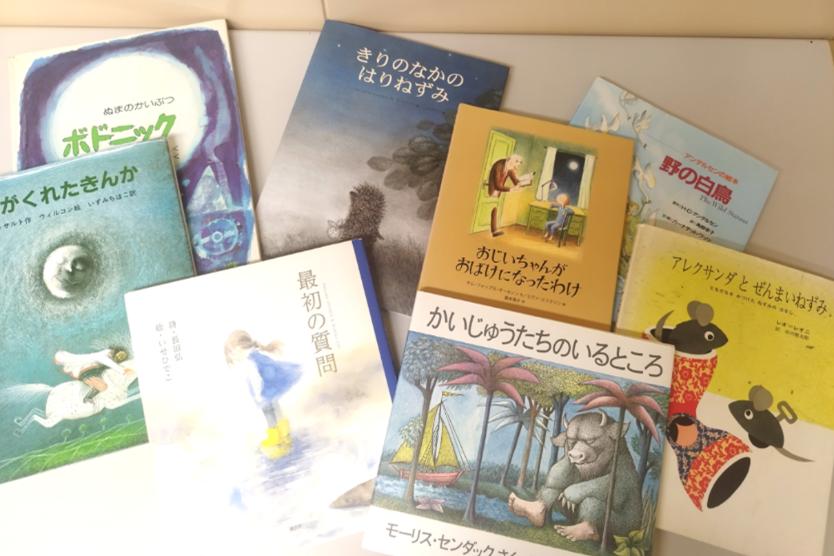
2025年こころを語る会第1回「レジリエンスの自己理解」
アンケート結果(回答13人)
《満足度》
少し満足した:2人
まあまあ満足した:6人
とても満足した:5人
《良かった内容(複数回答)》
レジリエンスに関する資料:9人
レジリエンスを高める方法:5人
絵本を通してレジリエンスについて考える:8人
絵本を通したレジリエンスに関する対話:9人
レジリエンスに関する自己理解:9人
《感想(自由記述)》
・若い方とグループで対話する方法がとても良かったです。
・若いころに読んでいたら参考になると思った。
・自分と向き合う機会ができた。
・自分で考え、資料に書き込んだデータをもっと有効活用したい。
・初めて出会えた方と知り合いになれたこと、ありがたいです。
・とても参考になりました。学習したことを活用してみたいと思いました。
・本を読んで意見を言い合うのが楽しかった。
・初めてのワークで理解を深めるのは難しかったです。
・とても参考になるお話をしていただき、今後の生き方の参考にさせていただきます。
・レジリエンスについて絵本を通して理解が深められたと思います。絵本は直接的な対話というよりも絵本を通して対話をすることで話しやすいです。今回グループワークを通して様々な人と関わりましたが、人とつながることもレジリエンスを高めることにつながるのではないかと思いました。良い機会になりました。ありがとうございました。
・絵本は自分の考え方や行動を考え直す機会になる。
・良かったです。
《次回への期待》
・対話が増えるとありがたいです。
・若い人との交流。
・参加者の興味を引く企画を掘り下げたい。
・次回も参加したいです。
・落ち込んだ時の乗り越え方を具体的にお話していただければ嬉しいです。
【総括と今後の展開について】
・レジリエンスの自己理解に関するアンケートは、参加者が回答して、それに対する三島先生のコメントなどのフィードバックは、第1回「こころを語る会」終了後の作業になります。プライバシーに十分配慮した対応をしますので、多くの参加者がアンケート回答に参加して欲しいと願っています。
・レジリエンスの自己理解とワークについては、配付された資料の説明を限られた時間内での説明では、フォローするのが難しい部分がありました。参加者の皆さんはもう一度資料を読み直して、自分なりにレジリエンスの理解を深め、ホームワークに取り組んでいただきたいと思います。これによって、レジリエンスの向上が可能になると思います。
・絵本のワークは、各グループの中での対話を活発にする上で、大変効果があったと思います。3グループに分かれてそれぞれの絵本に関する対話が行われましたが、他グループの記録がとれなかったことは心残りです。各グループでのファシリテータをその場で指名して、記録も担当していただくのは、ぶっつけ本番では難しかったです。大学生のサポータに記録をお願いするのも酷ですし、次回からのグループ分けとファシリテータの選出には工夫が必要と考えます。絵本のワークは、アンケート回答にもあるように大変好評でした。
次回は9月20日(土)の予定です。以下の内容を考えています。
☆第1回「こころを語る会」のワークで提示したホームワークの効果についての対話
☆物語を作るワーク
☆物語を作るワークと関連した薄井の著作「臨床心理学教室のパンプキンさん」の書評
以上、総括として、「こころを語る会」はマンネリ化を避けつつ、新しい試みを駆使して、参加者の「こころのしなやかさ」を強化することに、活動していきます。この会は、途中からの参加も歓迎します。
報告者: 薄井 洋基 (宇部環境コミュニティー理事)



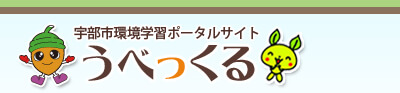





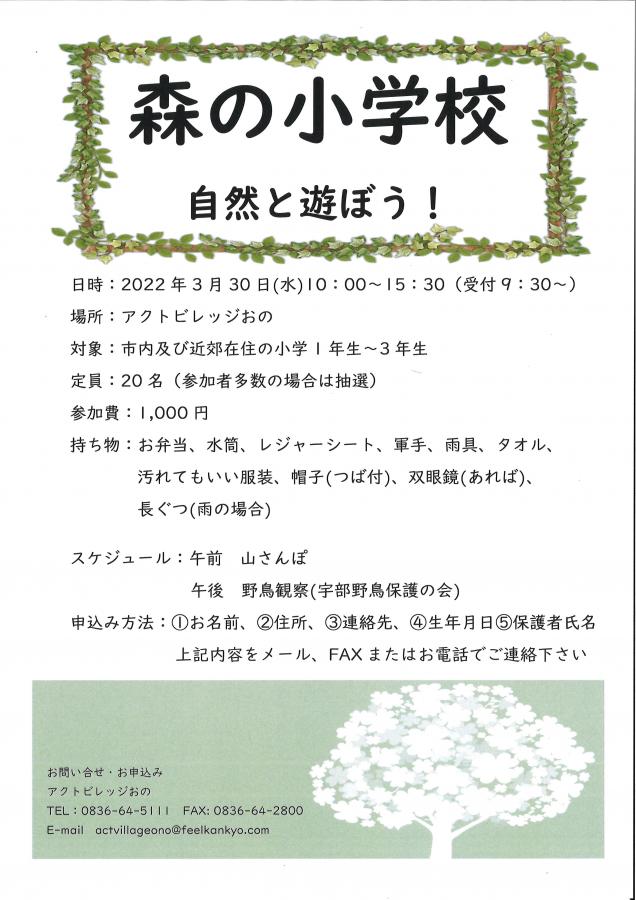


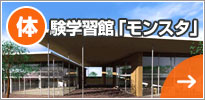

この記事のURL: http://ubekuru.com/blog_view.php?id=6212
◆ 現在、コメントはありません。
この記事へコメントを投稿します。